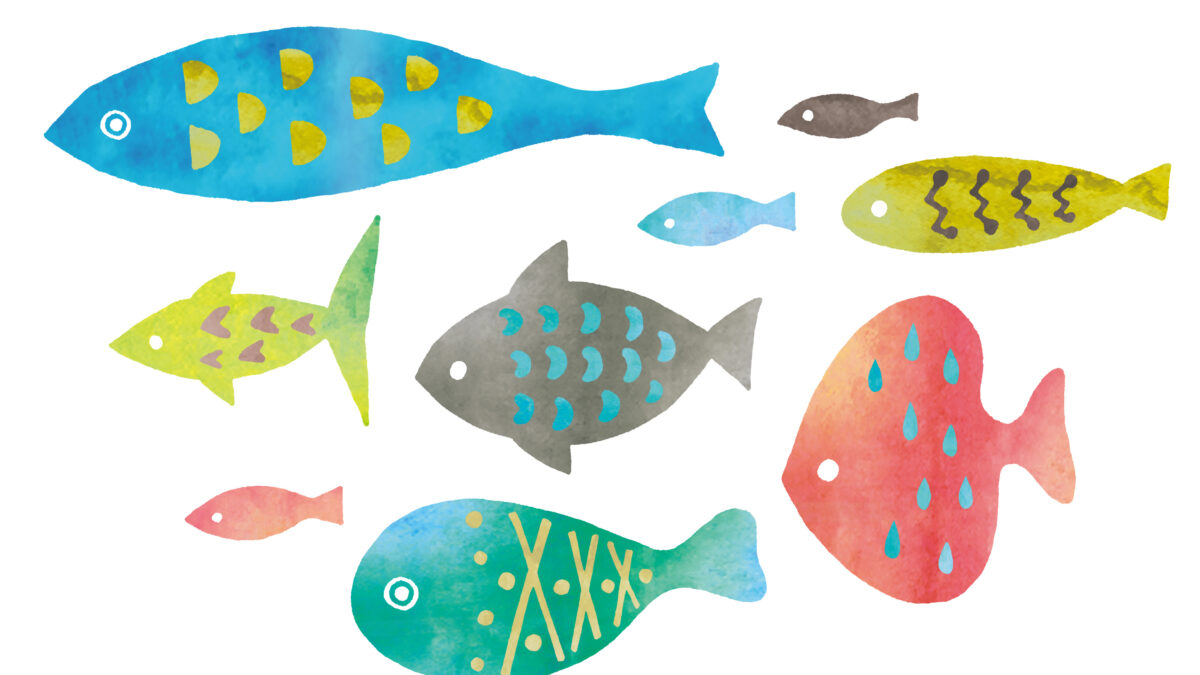水産は毎年安定して水揚げがあるものではなく、養殖と言えど安定した出荷が思うようにいかないこともあります。さらに昨今では海温上昇などの自然条件や世界情勢に左右され非常に不安定で相場が急騰することも多くなっており、かつ輸送コストや人材不足など、業界を取り巻く状況は厳しさを増しています。その中で、自社ECサイト(直販サイト・オンラインショップ)の運営は、水産の販路拡大、収益アップに繋がる新たなデジタル戦略として注目を集めています。自社ECサイトを活用することで、水産加工・水産卸業者自身が直接消費者に商品を届けられるため、収益率の向上やブランド力を強化できます。本記事では、自社ECサイトを活用して水産の販路拡大・収益を最大化する方法を具体的に解説します。
[toc]
漁業者・水産加工所直送!自社ECサイト運営のメリット
水産収益アップ・利益率の向上
仲介業者を介さず、直接消費者にお届けすることができるため、利益率を向上が見込めます。例えば、混獲されてきた魚なども価格を自由に決め、その日に販売することも可能です。1尾から販売することも可能なので、ができます。そして仲介業者を通さずに直接消費者へ販売することができるため、利益率の向上が見込めます。
全国への販路拡大・24時間いつでも注文可能
インターネットを通じて販売をするため、一気に販路を全国へと拡大することができます。また注文自体は24時間いつでも注文できますので、寝てる間や、水揚げ・加工作業中でもご注文を受け付けすることができます。
数の少ない混獲魚やもったいない魚も売れる!
特定の魚種を狙っても他の魚も入ってくることや極端に数が増減するような場合でも、自社ECサイトであればその日に水揚げされた魚を1尾から販売することも可能です。また、どの魚が水揚げされるかわからない場合でも、その日の鮮魚おまかせセットなど柔軟に販売形態を変えて販売することができます。また、あらかじめシーズンの漁模様を予測して、余裕をもった数で予約を受け付けることが可能になります。旬の魚など、さばく体験も合わせて消費者が楽しめるような商品づくりをすることで、加工する手間なく、マルの魚を販売することも可能です。
自社顧客の獲得

自社ECサイトを活用することで、消費者と直接つながりを持つことが可能になります。例えば、購入したお客様が、毎年旬の水揚げ時期にリピート購入をしてくださることで安定して売上を期待できます。また、購入者からのレビューや意見を参考にして商品改善を行うことで、顧客満足度を向上させることができます。
自社のブランド強化
自社ECサイトを活用することで、水産会社独自のブランドを確立し、消費者にアピールすることができます。例えば、加工過程や地域特有の魅力をストーリーとして発信することで、他の商品との差別化を図ることが可能です。また、商品パッケージやロゴデザインにこだわることで、視覚的な訴求力を高め、消費者の記憶に残りやすいブランドを築けます。
漁業者・水産加工所直送!自社ECサイト運営のデメリット
EC運営スキルが必要
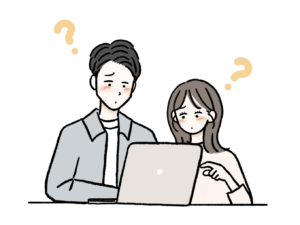
ECサイトの運営には、商品登録、注文管理、マーケティング活動(SNS活用や広告運用など)など、多岐にわたるスキルが求められます。特に、広告やデータ分析を行う知識が不足している場合、集客や売上向上が難しくなる可能性があります。また、これらのスキルを学ぶ時間やリソースの確保も課題となります。
顧客対応(クレームなど)

自社で直接販売を行う場合、顧客からの問い合わせやクレームへの対応が発生します。例えば、商品に不備があった際の交換や返金対応、配送の遅延に関する問い合わせなど、消費者とのコミュニケーションが増えることが予想されます。水産物(特に鮮魚)は消費者も扱いに慣れていないこともあるため、これらの対応には時間と労力が必要で、特に繁忙期にはリソースが不足しがちです。
個別配送や梱包の手間
消費者向けの直接販売では、商品の梱包や配送を個別に行う必要があります。これにより、これまで加工作業に集中していた時間を割くことになり、物流コストも増加します。特に商品の鮮度を保つための特殊な梱包やクール便であっても氷や保冷剤を利用するなど、作業の負担が大きくなる点も課題です。
EC構築の初期費用やシステム利用料

ECサイトを構築する際には、初期費用やデザイン料、機能追加にかかるコストが発生します。さらに、ショッピングカートのシステムを利用する場合、毎月のシステム利用料や決済手数料が必要となります。これらの費用は売上が軌道に乗るまでの間、水産業の収益に影響を与える可能性があります。
水産にデジタル戦略を取り入れる重要性
水産におけるデジタルシフトは、単に収益向上を目指すだけでなく、持続可能な経営を実現するための鍵となります。特に自社ECサイトは最近注目されており、以下のような効果を見込んで、水産業者が直接運営するECサイトも増えています。水産のデジタル戦略を考える上で参考にしてください。
大口卸先への依存を分散
ある大口の卸先に依存してしまうと、その時期の交渉価格次第で一気に収益率が変わってしまい、水産収益に大きな影響を及ぼします。特に水産物は相場が急騰することや予測より水揚げ数が少なくなることなどに対応することが非常に難しくなっています。自社の顧客を育てて、毎年自分の獲った・加工した水産物を楽しみに待ってくださるファンをつくることで、大口依存のリスクを低減することにもなります。
未来への安定した売上づくり

消費者の方へ直接、自社の商品を販売するため、利益率が確保できるだけでなく、水揚げが少ない場合や豊漁で相場が下がり儲けが出ない時などにも、自分の商品の価格を自分で決められるので、変化に強い事業をつくることができます。地道に増やした自社のファンは、毎年あなたの水揚げした、加工した商品を楽しみにしてくれます。今のうちから自社のファンを育てることで未来へ安定した売り上げづくりが可能となります。
デジタルシフトを始めるための第一歩
専門用語やカタカナを覚えるのは苦手な方も多いと思います。現在は無料で簡単に始められるECサイトも多数あります。勉強するよりもまずは一歩踏み出して、実際に触ってみると意外とできることもありますので、興味がある方はまず触ってみることをオススメします。
- 簡単なEC構築ツール:初心者でも利用しやすいシステムを使って始める
- 小規模スタート:品目を絞り、数量も少量から販売を始めてみる
- 専門家の活用:地域のIT支援やECコンサルタントを活用してサポートを受ける
本格的に販売を強化してみたい。ECサイトに力を入れたい。という方は最初から色々な知識やノウハウを持ったECコンサルタントへ相談することをオススメいたします。お気軽にご相談ください。(初回無料)
まとめ
水産業は、自然条件や市場価格の変動により収益が不安定で、近年では輸送コストや人材不足も課題となっています。こうした状況の中、自社ECサイトの運営は、収益率向上やブランド力強化を可能にする新たな販路拡大の手段として注目されています。自社ECサイトを活用すれば、消費者との直接的なつながりを築き、混獲魚や規格外品の販売、予約販売など柔軟な対応が可能です。一方で、顧客対応や物流コスト、EC運営スキルの必要性など課題もありますが、デジタル技術を活用することで、持続可能な経営と安定した収益基盤を築ける可能性があります。初めの一歩を踏み出すことで、水産業の未来を切り開くチャンスが広がります。